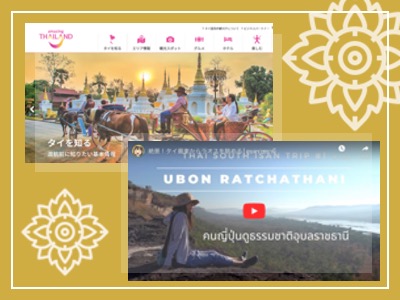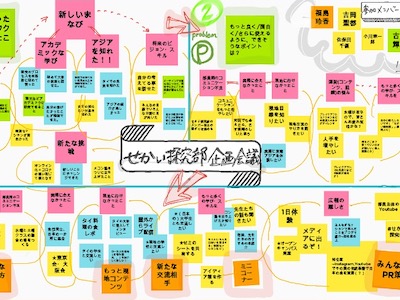3期生からの新企画、せかい探究部と上智大学とのコラボ授業の4回目(最終回) を12月14日(水)に実施しました。
コラボ授業での活動をふりかえりつつ、高校生・大学生ともにこれからの学びを考えるまとめのセッションとして、前半は「探究コラボチャレンジ」の振り返り、後半は「大学での学び」を共に考える発展的な対話としました。
まずは2回のセッションを通して行った「探究コラボチャレンジ」の振り返りです。せかい探究部高校生メンバーの探究を一歩前進させることを目指し、チームの高校生と大学生、あるいは高校生同士・大学生同士の間でもたくさん対話をしながら取り組んできました。
探究コラボチャレンジを通じて得た「自分にとっての学び」と「チームメンバーそれぞれから学んだこと」を、オンライン付箋ツールJamboardに書き出し、チーム内で互いにシェアし合いました。
高校生と大学生がお互いから学んだだけでなく、高校生同士、大学生同士からも様々な気づきや学びがあったようです。
チームメンバーそれぞれがどんなことを考えていたのかが交換できたとともに、相手の良いところへの気づきや・感謝も共有できたりと温かい場が形成され、良い機会となりました。


各チームでの振り返りを踏まえた全体でのまとめとしては、他者と関わることによる協同的な学びの考え方について紹介し、「探究コラボチャレンジ」やその振り返りでの経験・体感を持って協同的探究学習の面白さや意義をメタ的に捉えてもらうことを試みました。
そして、全4回のコラボ授業の総括・今後につなげる活動として、高大連携の学びの機会を活用し、各自の探究テーマの枠を超えたより大きなテーマでの探究学習を試みました。
お題は、「あなたにとって「大学」とは?」。
自身のこれまでの学びや学びに対する感覚、お互いに見てきた高校生・大学生の姿を踏まえながら、「大学」というものに対する考えを対話で深めてもらいました。
それぞれ自分の考えを紙に書き出してもらった後、高校生・大学生混合のランダムのブレイクアウトルームに分かれて共有し、半構造化インタビューで学んだスキルも取り入れながら、お互いに質問し合ったりやそれぞれの考えを交換したりしながら、深めていきました。


「自分がやりたいことを精一杯探究する環境を与えてくれる場所」「様々な角度で物事を見る思考力を養うところ」など、この高大連携のプロジェクトでの経験を含めつつ、自らの経験や考えをもとに多様なアイデアが出ていました。
実際の大学の授業の場を使い、学びの主体である高校生・大学生が自らの日々の生きた経験や考えを出し合うことで、「大学」というものを、生きた議論を通じて深く考えてもらう機会になったでしょうか。


せかい探究部初の試みとなる、上智大学とのコラボ授業の全4回が終了しました。初回では緊張の面持ちだった高校生と大学生も、4回目にはすっかり打ち解けて、コラボ授業の終わりを名残惜しそうにする様子が窺えました。
最後はみんなでせかい探究部「わくわくポーズ」で集合写真。上智大学のみなさんにもポーズを決めていただきました。

高大のコラボを通じて得た学びと経験をもとに、参加した高校生・大学生一人一人がこれから先も自らの学びの場を創造していってほしいです。
今回の授業を終えたコメントの一部を紹介します。
せかい探究部高校生の感想:
漠然とした興味に対して様々な視点からいろいろな切り込みを入れてくださって、たくさんの人と話し合うことの大切さを実感できました。大学で専門的なことをたくさん学ばれているので、着目する点やはっきりするべきところも私にはない視点を持っていて、勉強になりました。
自分の研究テーマに真摯に向き合ってくださる姿勢を近くで見て、このような大学生になりたいなと思いました。また、私の研究テーマが自分の専攻ではなくても興味を持ってくださったので嬉しかったです。このような場がこれからも増えればと思います!
2、3回目とは違う話題でお話しできて楽しかったです!全部の振り返りをジャムボードを使ってできてよかったですし感謝の気持ちを伝えることができてよかったです。
それぞれの立場から「大学」について話すのが面白かったです。大学生と高校生でも意見は違いましたが、大学三年生と一年生で意見が違うのも少し意外で面白かったです。
今回はまた新しい方とグループになる機会があったので、新しい価値観に触れることができ刺激的でした。大学生の方から見た大学の定義を聞くという実体験に基づいた考察は、自分の将来像のイメージに大きく繋がりましたし、その考えもあったか!という発見もあって、とても面白かったです。
大学生に自分の興味・関心を聞いてもらい、アドバイスしてもらう機会なんてないので本当に良い機会になったと思います。人に自分の探究を話すことで、自分の中で整理でき、色々と明確になったと思います。
大学生の感想:
最も大きな学びは、探究的な学びがどんなものであるかを体験を通して理解できたことである。学ぶ主体者のみならず、その周囲の複数の人の関与が不可欠な学びであり、高校生本人の学ぶ意思や、興味関心は何よりも大切であるが、それを追求するためには様々な人が関わり、意見を交流している。多くの人が関与してこそ、より良い深い学びが形成されると気づいた。
目指す成長地点はみんなそれぞれ異なっていて良いのだという点が最も印象的な学びでした。各々が現時点よりも一歩先に進むことを目標に適切なゴールを捉えてそこに向かってプロセスを築いていくということが、結果的には大きなことを成し遂げるルートになるのであり、成果の点でも人間性の観点でも大きな成長が出来る方法だと学びました。
最後の高校生とのコラボチャレンジの総括を通して、お互いに多様な意見を交わし合って考え方を広めることができたので本当によかったと思う。高校生は大学はどんな感じか、どんな研究を行っているのかを新しく知り、大学生は高校生がどのような着眼点を持って、またどんな疑問から研究を進めているのかのプロセスを知ることができた。
今回の授業では、同じグループの人たちと感想や感謝の言葉を伝えあった。建設的な議論をするために、時にはクリティカルになることも大事だが、このような形で相手の良いところを見つけてそれをシェアすると、言った側も言われた側も非常に気持ちが良くなると思った。
高校生の方と振り返りを行ったり、大学とはどのような場所かを一緒に考えることを通して、自分の高校時代の気持ちを思い出すことができました。ここで思い出したことを通して、限りある大学生活を充実したものにしていけれたらなと思いました。
初めての試みとなった、「上智大学×せかい探究部コラボ授業」も、あっという間の約1ヶ月間で全4回のセッションが終わりました。探究をきっかけとして、高校生・大学生、そして教員・スタッフメンバーにとっても新しい「せかい」が拓けた機会になったのではないかと思います。またここでの学びや感じたわくわく感をさらに広げていくべく、取り組んでいきたいと思います。
せかい探究部メンバー、そして、上智大生のみなさん、一緒に新たな場を創る活動への積極的な参加、本当にありがとうございました。
(共同執筆:新江梨佳 せかい探究部監督/上智大特任助教 & 板橋未和 上智大3年/SophiaGEDインターン)